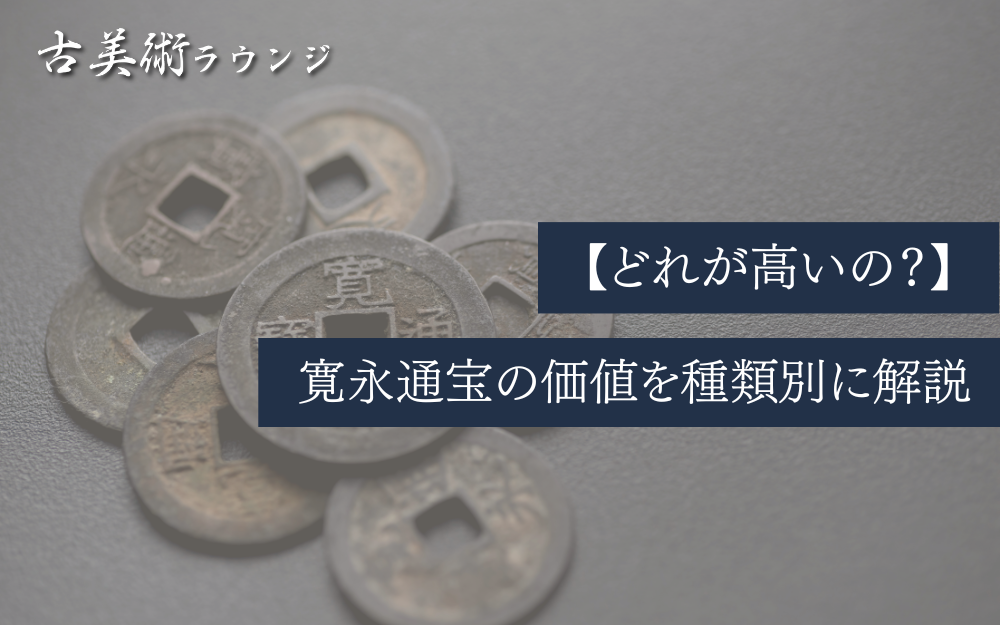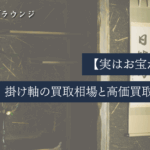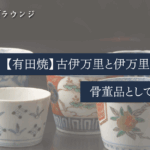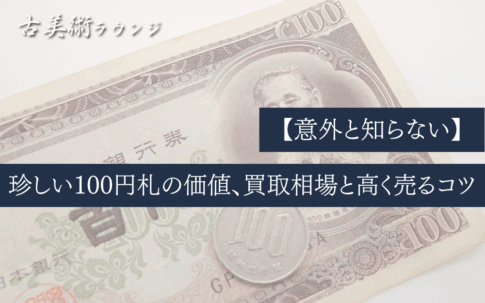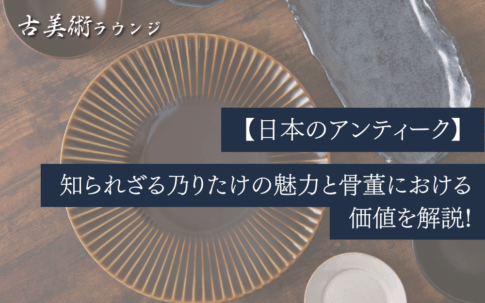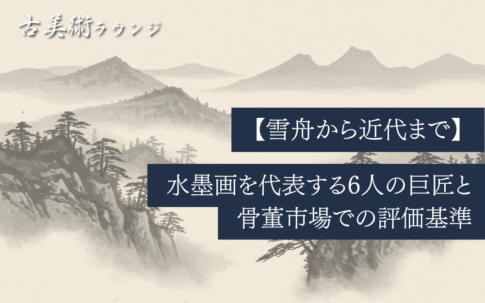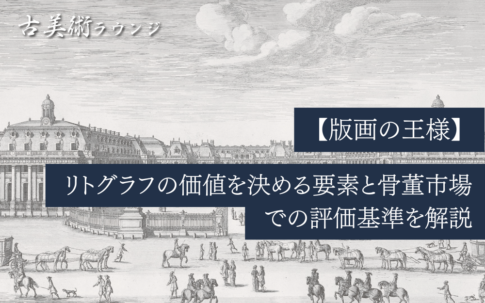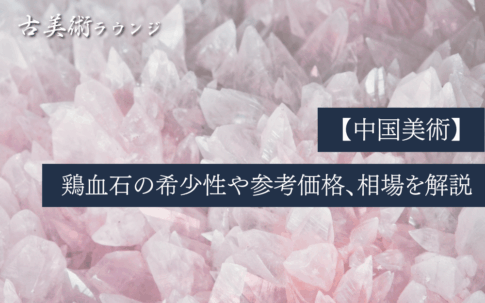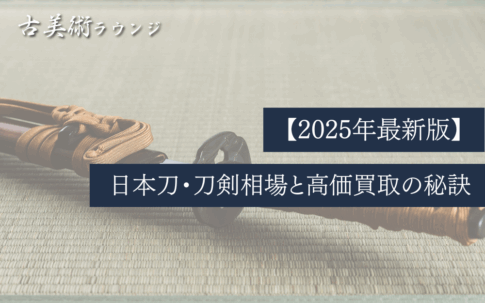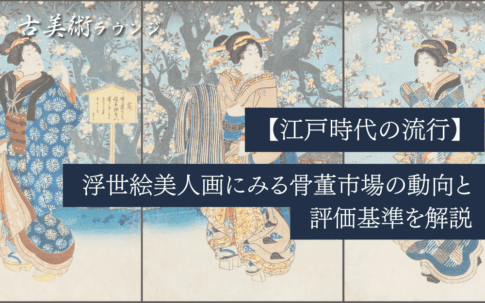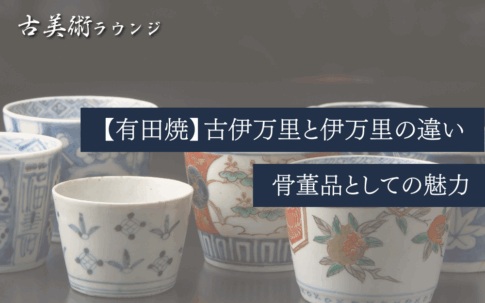江戸時代から昭和まで約300年間も使われ続けた「寛永通宝」。遺品整理や古い物の整理の際に見つけることが多いこの古銭ですが、実は種類によって価値に大きな差があることをご存知でしょうか?
一般的な寛永通宝は数十円程度の価値しかありませんが、中には数十万円の価値を持つものも存在します。この価値の違いを知らずに処分してしまうのは非常にもったいないことです。
この記事でわかること
・寛永通宝の種類別価値と相場
・高額な寛永通宝の見分け方
・査定時のポイントと注意点
・適切な売却方法
当記事では、古銭専門家の知見と最新の市場データを基に、寛永通宝の真の価値を詳しく解説します。
寛永通宝の基礎知識

寛永通宝とは?江戸時代を支えた庶民の通貨
寛永通宝は、1626年(寛永3年)から1953年(昭和28年)まで実に327年間流通していた日本の銅銭です。表面には「寛永通宝」の4文字が刻まれ、中央には四角い穴が開いた「穴銭」として知られています。
当時の価値は一文銭で約37.5円、四文銭で約150円でした(※1)。庶民の日常的な買い物に使われ、江戸時代の経済を底支えしていた重要な通貨です。
※1 参照元:造幣局「貨幣の歴史」
古寛永と新寛永の違いと見分け方
寛永通宝は発行時期により大きく2つに分類されます。
- 初期の寛永通宝で、各地で個別に鋳造
- 文字の書体や品質にばらつきがある
- 手作業による風合いが強く、希少性が高い
- 幕府直轄の亀戸などで規格化して大量生産
- 品質が均一で、裏面に鋳造地を示す文字が刻まれることが多い
- 流通量が多く、一般的には価値が低い
母銭と子銭の違い
母銭(ぼせん):子銭を作るための型となる原型銭
- 精密な作りで品質が非常に高い
- 現存数が極めて少ない
- 同じ種類でも子銭の数十倍〜数百倍の価値
子銭(こせん):実際に流通していた通用銭
- 大量生産されたため現存数が多い
- 一般的な寛永通宝の多くがこれに該当
【高額】プレミア価値のある寛永通宝

島屋文(しまやぶん):10万円〜30万円
特徴と見分け方
島屋文は新寛永初期の1668年頃に鋳造された、最も価値の高い寛永通宝として知られています。

▼主な特徴
- 「通」の右上部分が「マ」ではなく「ユ」のような形
- 裏面に「文」の文字(島屋文)または無背(島屋無背文)
- 文字全体に丸みがある「島屋」書体
なぜ高額なのか?
島屋文は新寛永通宝の中でも珍しい種類の一つで、その特異な様式から他の新寛永通宝との見分けは容易です。ただし、島屋文の鋳造の経緯や目的については、まだ不明な点が多く残されています。
発行枚数が極めて少なく、新寛永の最高傑作と称される美しい出来映えが高い評価を受けています(※2)。
市場での取引事例
- 美品の島屋文:20万円〜30万円
- 島屋無背文:10万円〜15万円
- 母銭の場合:さらに高値の可能性
※2 参照元:日本貨幣商協同組合「古銭価格動向調査 2024年版」
二水永(にすいえい):1万円〜5万円
「永」の字の特殊性
二水永は寛永通宝の中でも最も古い1626年に鋳造された歴史的価値の高い古銭です。

▼識別ポイント
- 裏面に「三」または「十三」の文字
- 「永」の字が「二」と「水」を組み合わせたような独特の形
- 佐藤新助の没後、鋳造は一時中断しますが、寛永12年(1635年)に息子の佐藤庄兵衛が再開。この時の二水永は裏面に「十三」と刻印されたといわれ、寛永13年の鋳造と考えられています。
歴史的意義
二水永は寛永通宝の初期に鋳造された特殊な一文銭です。寛永3年(1626年)に常陸水戸の豪商「佐藤新助」が幕府と水戸藩の許可を得て私的に鋳造したのが始まりとされています。
寛永通宝の「生みの親」とも言える佐藤新助が手がけた記念すべき最初期の作品として、コレクターから高い人気を集めています。
日光御用銭(にっこうごようせん):10万円〜25万円
徳川家との関係
日光御用銭は、江戸時代の正徳4年(1714年)に鋳造された新寛永通宝です。日光御用銭の特徴は、銭文で「寳(宝)」文字内の「尓」にハネのないことが大きなポイントです。

▼特徴的な書体
- 「寳」の文字の「尓」部分にハネがない
- 直径26.4〜26.6mmと大型
- 母銭に近い精密な作り
希少性の理由
日光御用銭については徳川家の日光参拝時の銭であるとの説がほとんどですが明確になっていない部分も多く、この後で取り上げる「正徳期佐渡銭」と書体が非常に似ていることから、それの一種ではないかとの説もあります。
徳川将軍家の日光東照宮参拝に関連して特別に鋳造されたとされる特殊な背景が、その希少価値を高めています。
背広佐(せびろさ):数万円〜35万円
佐渡銭の特徴
享保期背広佐銭は、江戸時代の新寛永通宝の一種で、享保2年(1717年)に佐渡で鋳造された銭貨です。

▼識別要素
- 裏面に大きく明瞭な「佐」の文字
- 「佐」の4画目(斜線)が特徴的に長い
- 複数の書体バリエーションが存在
書体による価値の違い
価値的には、享保期背広佐銭は数百円から一千円程度、母銭であれば数十万円となることも珍しくありません。享保期の背佐は書体がいくつも存在するため、専門家による査定が欠かせない逸品です。
佐渡金山の豊富な銅を使用し、高品質な銅で製造されたことから、白銅に近い美しい色合いを持つものが多く見られます。
【中程度】数千円〜数万円の価値がある種類

松本銭:5千円〜1万円
「寶」の字の特徴
松本銭の最大の特徴は、「寳(宝)」の字の左半分が大きく右上方に傾いているように見える独特の字形にあります。この「斜宝」と呼ばれる書体が、松本銭を他の初期寛永通宝から一目で見分ける大きな特徴となっています。
1637年に信濃国松本で鋳造された古寛永で、発行枚数の少なさから博物館展示品レベルの希少価値を持ちます。
偽物への注意点
価値が高いことから偽物が大量に製造された過去があります。今所持している松本銭が偽物だと価値はつかないことを覚えておきましょう。
高い価値ゆえに贋作も多く出回っているため、専門家による真贋鑑定が不可欠です。
石ノ巻銭:1千円〜1万円
「仙」の文字の意味
石ノ巻銭は、宮城県の仙台市や石巻市で1728年に鋳造された新寛永です。
裏面の上部に「仙」と書かれているものとないものが存在します。「寛永通宝」の字体が幅広で「通」のしんにょうが通常よりも多くひねっているのが特徴です。
「仙」は仙台藩を示す文字で、地方分権的な貨幣制度の特徴を表しています。
書体のバリエーション
- 「重揮通背仙」:「通」の辶部分に特徴的な折れがある
- 「重揮通無背」:裏面に文字がないタイプ
- コ頭、マ頭など細かな書体の違い
書体により価値が大きく変動するため、専門的な鑑定が必要です。
退点文・正字入文:数千円〜6万円
文字の特徴的な違い
退点文
退点文は、1668年に発行された銭貨で、文銭の一種です。
退点文の書体は、「文」についているなべぶたの点が右に寄っているという珍しい特徴を持っていることから退点と呼ばれており、この退点が退点文の名前の由来となっています。
正字入文
正字入文は、退点文と同じ1668年に発行された銭貨で、新寛永に分類されます。
文字が標準的な書体である「正字」で書かれていることや、「文」のなべぶたの下側が「入」に見えることが正字入文の大きな特徴です。
母銭と子銭の価値差
- 子銭:数百円〜数千円
- 母銭:数万円〜十数万円
同じ種類でも母銭かどうかで価値が大幅に変わります。
その他の地方銭
水戸銭:数百円〜8千円
- 水戸銭の特徴は、「永」の字で左側の縦画が太く、力強い印象を与えることにあります。この独特の「力永」と呼ばれる書体が、水戸銭を他の寛永通宝から見分ける際の重要なポイントになっています。
- 書体の種類により価値に差がある
浅草銭:500円〜1,500円
- 浅草銭の特徴は、他の初期寛永通宝と比べて比較的均質な出来であることが挙げられます。これは、浅草の鋳造所が幕府の直轄管理下にあり、品質管理が徹底されていたことを示唆しています。
芝銭:数十円〜500円
- 芝銭の特徴は、「通」の字の上部が草書体になっている「草点」と呼ばれる書体が多いことです。また、「永」の字も特徴的な形をしています。
- 最初に鋳造された寛永通宝として歴史的価値あり
【基本】一般的な寛永通宝の価値

正字背文などの標準的な種類
多くの寛永通宝は以下のような標準的な種類に該当し、価値は比較的低くなります。
正字背文:数十円〜500円
- 正字背文は、1688年に発行された寛永通宝で、新寛永に分類されます。
裏面に「文」という文字が刻まれてるのが特徴的で、そこから正字背文と呼ばれるようになりました。
現存数が非常に多いことから、価値はそこまで高くありません。
小梅銭:500円〜1千円
- 小梅銭は、江戸時代後期の寛永通宝で、元文2年(1737年)に江戸の小梅村(現在の東京都墨田区)で鋳造されたとされる銭貨です。
- 裏面に「小」の文字、狭穿(穴が小さい)が特徴
下野国足尾銭:100円〜500円
- 下野国足尾銭は、1741年に発行された新寛永に分類される銭貨です。背面の上部に「足」の文字が書かれていることから、別命「足字銭」とも呼ばれています。
- サイズにばらつきがあり、大きいほど高値
なぜ価値が低いのか?

▼一般的な寛永通宝の価値が低い理由。
- 希少性の欠如
- 大量生産による現存数の多さ
- 技術向上による品質の均一化
- 長期間の流通による摩耗
それでも査定に出す意味
価値が低いとされる寛永通宝でも、以下の可能性があるため査定をお勧めします。

- 書体の違いによる付加価値
- 母銭である可能性
- 保存状態による価値向上
- セット販売による価格上昇
寛永通宝の価値を決める要因

希少性(発行枚数)
価値を決める最も重要な要因は希少性です。
超高額(10万円以上)
- 島屋文、日光御用銭、背広佐など
- 発行枚数が極めて少ない特殊な銭貨
高額(1万円以上)
- 二水永、松本銭など
- 初期古寛永や地方特色の強い銭貨
中程度(千円以上)
- 石ノ巻銭、退点文、正字入文など
- ある程度の希少性を持つ銭貨
一般的(数百円以下)
- 正字背文、芝銭、浅草銭など
- 大量生産された標準的な銭貨
保存状態の重要性
同じ種類でも保存状態により価値は大きく変動します。
優品(美品)
- 文字がくっきりと読める
- 摩耗や錆びが少ない
- 市場価格の上限に近い値段
普通品
- 多少の摩耗や汚れがある
- 文字は判読可能
- 市場価格の標準的な値段
劣品
- 摩耗が激しく文字が不明瞭
- 錆びや欠けが目立つ
- 大幅な価格下落
歴史的意義

特定の歴史的背景を持つ寛永通宝は付加価値があります。
- 技術革新品:鋳造技術の発達を示す例
- 初期鋳造品:寛永通宝制度の成立過程を示す
- 地方特色品:江戸時代の地方経済を反映
母銭かどうかの判断
母銭の特徴
- 精密な仕上がり:文字が非常に鮮明
- 重量:同種の子銭より重い場合が多い
- 材質:より良質な銅を使用
- 希少性:同種の子銭に比べて現存数が極少
母銭と判定されれば、子銭の数十倍の価値になることも珍しくありません。
寛永通宝を高く売るための実践的なコツ

査定前の準備と注意点
やってはいけないこと
- 無理な清掃:価値を損なう可能性
- 研磨:表面を傷つけるリスク
- 化学薬品の使用:材質を変化させる危険
適切な準備
- 現状維持:触らずそのままの状態で保管
- 写真撮影:表裏両面を鮮明に撮影
- 付属品の保管:箱や説明書があれば一緒に
複数業者での査定の重要性
約半数の消費者が骨董品の価値判断に不安を抱いている現状は、業界全体にとって大きな機会でもあります。
推奨する査定方法

- 最低3社での比較査定
- 専門性の高い業者の選択
- 査定根拠の詳細な説明を求める
- 契約条件の確認
業者選びのポイント
骨董業者の選び方で詳しく解説していますが、特に以下の点を重視してください。

- 透明性の高い査定説明
- 古銭分野での専門実績
- 適正な査定料金体系
- アフターフォローの充実
適切な保管方法
保管環境
- 湿度管理:湿気を避ける
- 温度安定:急激な温度変化を避ける
- 直射日光回避:紫外線による劣化防止
保管用品
- コインホルダー:専用のプラスチックケース
- 密閉容器:湿気や埃を防ぐ
- 手袋着用:皮脂による汚れ防止
査定時に伝えるべき情報
入手経路
- 相続品・遺品整理で発見
- 購入時期と購入先
- 保管状況と保管期間
付随情報
- 他の古銭との関連性
- 保管時の特別な配慮
- 過去の鑑定歴があれば提示
寛永通宝の査定でよくある質問

Q1: 汚れや錆びがあっても価値はあるか?
A: はい、汚れや錆びがあっても希少種であれば十分価値があります。
汚れやサビがひどいようなものでも、販売ルートが広いことで高価買取される可能性があるでしょう。むしろ、素人判断での清掃で価値を損なうリスクの方が高いため、現状のまま査定に出すことをお勧めします。
Q2: どこで査定してもらうべきか?
A: 古銭専門の知識を持つ査定士がいる業者を選びましょう。
重要なポイント
- 古銭分野での専門実績
- 透明性の高い査定説明
- 複数業者での比較検討
- 適正な料金体系
詳しくは「骨董業者の選び方」をご参照ください。
Q3: 偽物の見分け方は?
A: 素人での真贋判定は非常に困難です。
特に以下の高額種については贋作も多いため、専門家による鑑定が不可欠
- 島屋文
- 松本銭
- 日光御用銭
- 二水永
警戒すべきポイント
- 異常に状態の良い高額種
- 不自然な価格での販売歴
- 出所不明の品物
Q4: 査定料はどのくらいかかる?
A: 多くの業者で基本査定は無料ですが、事前確認が重要です。
確認すべき費用
- 基本査定料
- 出張査定費
- 鑑定書発行費
- キャンセル料
Q5: まとめて査定に出すメリットは?
A: セット査定により価格が向上する可能性があります。
メリット
- セット価値:関連性のある組み合わせ
- 効率化:査定コストの削減
- 交渉力:まとめ売りによる価格交渉
まとめ

寛永通宝は種類により価値に大きな差がある古銭です。一般的には数十円程度の価値しかないものが多いですが、島屋文や日光御用銭などの希少種は数十万円の価値を持つ場合があります。
価値のある寛永通宝の特徴おさらい
超高額(10万円以上)
- 島屋文(「通」の右上が「ユ」字状)
- 日光御用銭(「寳」の「尓」にハネなし)
- 背広佐(裏面に大きな「佐」)
高額(1万円以上)
- 二水永(「永」が「二水」状)
- 松本銭(「寳」の左半分が右上に傾斜)
中程度(千円以上)
- 石ノ巻銭(裏面に「仙」)
- 退点文・正字入文(特徴的な「文」字)
専門業者への相談の重要性
消費者は「適正価格で取引したい」という強い願望を持っており、そのためには専門性と誠実さが不可欠と考えています。
寛永通宝の真の価値を知るには、専門知識を持った査定士による鑑定が不可欠です。特に以下の点で専門業者への相談をお勧めします。
- 正確な種類判定:微細な書体の違いの識別
- 真贋鑑定:贋作の見分けと本物の確認
- 適正価格評価:市場動向を反映した価格設定
- 売却方法の提案:最適な売却タイミングと方法
遺品整理や古い物の整理で寛永通宝を発見した場合は、処分する前に必ず専門業者に相談することで、思わぬ価値を見逃さずに済むでしょう。
適切な業者選びについては「骨董業者の選び方」で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。また、2025年の古美術市場トレンドも売却タイミングの参考になります。
関連記事: